カリウムは原子番号19の元素で、元素記号はKと表記されます。大部分は細胞内に存在し、浸透圧の調整、筋収縮、神経伝達などに関係しています。人体を構成する要素として、8〜9番目に多い物質です。体重のおよそ0.2%を占めており(60kgの成人ではおよそ120gのカリウムが含まれることになります)、主要なミネラルでカリウムより多いのはカルシウムやリンになります。
カリウムの働き
浸透圧バランスを保つ(血圧を下げる)
カリウムは細胞内に存在し、細胞外(血液)にナトリウムが存在しています。このナトリウムと密接に関係しながら浸透圧バランスを保っており、ナトリウムを排出させて血圧を下げる働きをします。
筋肉の収縮と弛緩を調節
カリウムはナトリウムと協力して筋肉の収縮と弛緩を調節する働きがあります。細胞膜を通じて細胞内に入ったり、細胞外へ出たりすることによって電気信号(活動電位)を発生させ、筋肉の伸縮運動を制御しています。
神経伝達物質
カリウムは体内で必要不可欠な電解質です。神経伝達を担う重要な役割があり、細胞間における情報伝達の働きに関わっています。
カリウムの排出
摂取したカリウムは小腸で吸収され、全身の細胞内へと供給されていきます。過剰に摂取したカリウムは腎臓から尿として排泄されます。
腎臓病などで腎機能が低下するとカリウムの排出がうまくいかず、高カリウム血症になったりします。そのため腎臓病ではカリウム量を制限することがあります。
カリウムを多く含む食品
カリウムは色々な食品に含まれていますが、特に野菜や海藻、果物等に多く含まれています。
100g中の含有量は以下のとおりです。
切り干し大根(乾燥)……3200mg
パセリ……1000mg
干しブドウ……740mg
アボカド……720mg
ほうれん草……690mg
ひきわり納豆……700mg
大豆……570mg
里芋……560mg
にんにく……530mg
モロヘイヤ……530mg
にら……510mg
バナナ……360mg
納豆……660mg
にんにく……530mg
西洋かぼちゃ……430mg
たけのこ……470mg
にんじん……260mg
キウイフルーツ……290mg
カリウムの一日に必要な量
日本人の食事摂取基準によると、カリウムの目安量は成人男性で2500mg、目標量は3000mg以上。成人女性の目安量は2000mg、目標量は2600mg以上となっていますが、平成24年度国民健康栄養調査の結果では、カリウムの摂取量は中央値で1858mgで、目安量にも満たないのが現状です。
男性のカリウムの食事摂取基準
| 目安量 (mg/日) |
目標量 (mg/日) |
|
| 1~2(歳) | 900 | – |
| 3~5(歳) | 1,100 | – |
| 6~7(歳) | 1,300 | 1800以上 |
| 8~9(歳) | 1,600 | 2000以上 |
| 10~11(歳) | 1,900 | 2200以上 |
| 12~14(歳) | 2,400 | 2600以上 |
| 15~17(歳) | 2,800 | 3000以上 |
| 18~29(歳) | 2,500 | 3000以上 |
| 30~49(歳) | 2,500 | 3000以上 |
| 50~69(歳) | 2,500 | 3000以上 |
| 70以上(歳) | 2,500 | 3000以上 |
女性のカリウムの食事摂取基準
| 目安量 (mg/日) |
目標量 (mg/日) |
|
| 1~2(歳) | 800 | – |
| 3~5(歳) | 1,000 | – |
| 6~7(歳) | 1,200 | 1800以上 |
| 8~9(歳) | 1,500 | 2000以上 |
| 10~11(歳) | 1,800 | 2000以上 |
| 12~14(歳) | 2,200 | 2400以上 |
| 15~17(歳) | 2,100 | 2600以上 |
| 18~29(歳) | 2,000 | 2600以上 |
| 30~49(歳) | 2,000 | 2600以上 |
| 50~69(歳) | 2,000 | 2600以上 |
| 70以上(歳) | 2,000 | 2600以上 |
| 妊婦 | 2,000 | – |
| 授乳婦 | 2,200 | – |
- 目安量は体の恒常性維持に適正と考えられる量と現在の日本人の摂取量から考慮した値です。
- 目標量は、高血圧を中心とした生活習慣病の発症予防および重症化予防の観点から設定されています。ただし腎機能に異常がある場合は摂取量に制限が必要と考えられます。専門家にご相談ください。
- 6歳未満では目標量の掲載はありませんが、該当年齢の目安量を参考に適度な摂取が大切です。
ダイエットとカリウム
カリウムの働きである、細胞内の浸透圧の調整が「うまくできなくなると、塩分や水分の代謝が悪くなり、老廃物が排出されにくくなります。
カリウムを摂取して不要な老廃物を排出し、新陳代謝が高めると、冷え性が解消し血行がよくなり痩せやすい体になります。
カリウムの不足(欠乏症)や過剰症
カリウムは色々な食品に含まれており、欠乏症になるほど欠乏することはめったにないのですが、積極的に摂取を進めたいミネラルの一つです。
カリウムが不足した時
激しい下痢や嘔吐などが続いたり、利尿剤を使用したりするとカリウムが不足する場合があります。
低カリウム血症
多尿、高血圧、疲労、筋力低下、神経機能の低下、不安、イライラ、抑うつ、睡眠障害、虚弱、便秘、乾燥肌などが症状として現れます。
カリウムが過剰な時
通常な状態であれば、余剰なカリウムは尿として排出されますが、腎機能が低下している場合、過剰にカリウムが体内に残ることになります。
高カリウム血症
四肢の痺れ、不整脈、頻脈、筋力低下、吐き気などが主な症状として現れます。



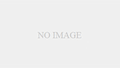
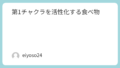
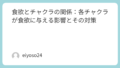
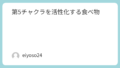
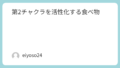
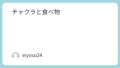
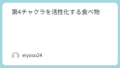
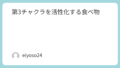
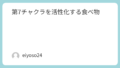
コメント