カリウムは私たちの体に必要なミネラルですが、腎臓の機能が低下すると体外へうまく排出できなくなり、血液中のカリウム濃度が異常に高くなる「高カリウム血症」を引き起こすことがあります。
- なぜカリウム制限が必要なのか
- カテゴリー別の詳細な食品カリウム含有量リスト(高カリウム順)
- 毎日の食事で無理なくカリウムを減らす調理のコツ
- 外食や加工食品選びの注意点
などを、網羅的に、そして分かりやすく解説します。この記事を参考に、正しい知識を身につけ、安心して食事療法を続けていきましょう。
1. なぜカリウム制限が必要なのでしょうか?
まず、食事管理の基本となるカリウムの役割と、制限が必要になる理由について深く理解しましょう。
体におけるカリウムの重要な役割
カリウムは、私たちの体内で非常に重要な役割を担う電解質の一つです。主な働きには以下のようなものがあります。
- 細胞の浸透圧の維持: ナトリウムとバランスを取りながら、細胞内外の水分量を適切に保ちます。
- 神経伝達のサポート: 筋肉の収縮や神経からの情報伝達をスムーズに行うために不可欠です。
- 血圧の調整: ナトリウムの排出を促し、血圧を正常に保つ働きがあります。
このように、カリウムは生命維持に欠かせないミネラルですが、その量は常に厳密にコントロールされている必要があります。
腎臓とカリウムの関係
このカリウムの体内バランスを調整しているのが「腎臓」です。健康な腎臓は、食事から摂取したカリウムのうち、体に必要な分だけを残し、余分なカリウムを尿として体外へ排出します。
しかし、慢性腎臓病(CKD)などが進行し腎機能が低下すると、このカリウムの排出能力が落ちてしまいます。その結果、体内にカリウムが溜まりやすくなり、血液中のカリウム濃度が基準値(3.5~5.0 mEq/L)を超えた「高カリウム血症」という状態に陥るのです。
高カリウム血症の危険性と症状
高カリウム血症は、初期段階では自覚症状がないことが多いですが、進行すると以下のような症状が現れることがあります。
- 初期症状: 指先のしびれ、味覚異常、全身の倦怠感、脱力感
- 重篤な症状: 筋力低下、吐き気、不整脈、心停止
特に、心臓の筋肉への影響は深刻で、突然の心停止を引き起こすリスクがあるため、腎臓病の患者さんにとってカリウムのコントロールは命を守るために不可欠なのです。
カリウム摂取量の目標値
一般的に、腎臓病でカリウム制限が必要な場合、1日の摂取目標量は1,500mg〜2,000mg以下に設定されることが多いです。これは、健康な成人の目標量(男性3,000mg以上、女性2,600mg以上)と比較すると、かなり厳しい制限であることがわかります。
ただし、必要な制限量は個々の病状や血液検査の結果によって異なります。必ず主治医や管理栄養士の指導に従い、ご自身の目標値を確認してください。
2.【カテゴリー別】食品カリウム含有量リスト(高カリウム順)
ここからは、具体的な食品のカリウム含有量をカテゴリー別に見ていきましょう。数値を比較しやすくするため、原則として可食部100gあたりのカリウム量で表記し、カリウムの多い順に並べ替えています。日々の食材選びの参考にしてください。
2-1. 果物・缶詰
果物はビタミンや食物繊維が豊富ですが、カリウムが多く含まれるものも少なくありません。特に生の果物やドライフルーツは注意が必要です。
【特にカリウムが多い果物(100gあたり250mg以上)】
| 品目 | カリウム (mg) | 備考 |
|---|---|---|
| バナナ | 360 | 中1本(約100g)で1日の目標量の約1/5に。 |
| メロン | 350 | 少量でも高カリウム。 |
| キウイフルーツ | 290 | 小ぶりのものでも意外と多い。 |
| マンゴー | 170 | 1個(200g)で340mgに達するため注意。 |
| 柿 | 170 | 1個(200g)で340mg。半分程度に。 |
| 梨 | 140 | 1個(200g)で280mg。 |
【比較的カリウムが少ない果物(100gあたり200mg未満)】
| 品目 | カリウム (mg) | 備考 |
|---|---|---|
| いよかん | 190 | |
| もも | 180 | |
| いちご | 170 | |
| びわ | 160 | |
| みかん | 150 | 小1個(70g)なら105mg。 |
| パイナップル | 150 | |
| グレープフルーツ | 140 | |
| りんご | 120 | カリウム制限中でも比較的選びやすい果物。 |
【缶詰・加工品】
缶詰は、シロップにカリウムが溶け出しているため、生の果物よりも含有量が少なくなります。
| 品目 | 量 | カリウム (mg) |
|---|---|---|
| パイン缶詰 | 100g | 120 |
| もも缶詰 | 100g | 80 |
| みかん缶詰 | 100g | 75 |
- ドライフルーツは避ける: レーズンや干し柿、プルーンなどは水分が抜けてカリウムが凝縮されているため、少量でも非常に高カリウムです。
- 缶詰は賢く利用: 果物が食べたい時は缶詰を選ぶのも一手です。ただし、カリウムが溶け出しているシロップは絶対に飲まないでください。
- 食べる量に注意: カリウムが少ないりんごでも、丸々1個食べれば摂取量は増えます。1日に食べる量を決め、少量を楽しむようにしましょう。
2-2. 飲料(お茶・ジュース・アルコール)
飲み物は無意識に多くの量を摂取しがちです。「見えないカリウム」に注意しましょう。
【ジュース類(100mlあたり)】
野菜や果物を凝縮したジュースは、生のものを食べる以上にカリウム密度が高くなります。
| 品目 | カリウム (mg) |
|---|---|
| 野菜ジュース | 200~350 |
| トマトジュース | 260 |
| オレンジ100%ジュース | 190 |
| パイン100%ジュース | 190 |
| グレープフルーツ100%ジュース | 160 |
| りんご100%ジュース | 110 |
| グレープ100%ジュース | 24 |
| アセロラ100%ジュース | 13 |
【お茶・コーヒー類(100mlあたり)】
| 品目 | カリウム (mg) | 備考 |
|---|---|---|
| 玉露 | 340 | 茶葉の成分がそのまま抽出されるため非常に高い。 |
| インスタントコーヒー(2g) | 72 | 1杯分 |
| ドリップコーヒー | 65 | |
| 番茶 | 32 | |
| 煎茶 | 27 | |
| ほうじ茶 | 24 | |
| ウーロン茶 | 13 | |
| 紅茶 | 8 | |
| 玄米茶 | 7 | |
| 麦茶 | 6 | カリウムが非常に少なく、水分補給に適している。 |
【アルコール類】
| 品目 | 量 | カリウム (mg) |
|---|---|---|
| 黒ビール | 350ml | 193 |
| ビール | 350ml | 119 |
| 赤ワイン | 100ml | 110 |
| 白ワイン | 100ml | 60 |
| 日本酒 | 1合(180ml) | 約10 |
| ウィスキー・ブランデー・焼酎 | 各種 | 微量 (ほぼ0) |
- 野菜ジュースはNG: 「手軽に野菜が摂れる」と思いがちですが、カリウム制限中は原則として避けましょう。
- 水分補給は麦茶が最適: カリウムが少なく、カフェインも含まない麦茶は日常的な水分補給に最適です。
- お酒を選ぶなら蒸留酒: ビールやワインなどの醸造酒には原料由来のカリウムが含まれます。飲むならウイスキーや焼酎などの蒸留酒を選びましょう。ただし、アルコール自体が肝臓や腎臓に負担をかけるため、飲酒量は医師に相談してください。
2-3. 野菜・芋類、豆類、海藻類
このカテゴリーにはカリウムが非常に多い食品が集中しています。しかし、調理法によってカリウムを大幅に減らすことができるため、正しい知識を持つことが最も重要です。
【特にカリウムが多い食品(生100gあたり)】
| 品目 | カリウム (mg) |
|---|---|
| ほうれん草 | 690 |
| 里芋 | 640 |
| 枝豆 | 590 |
| アボカド | 590 |
| さつまいも | 480 |
| かぼちゃ | 450 |
| じゃがいも | 420 |
| 納豆(1パック50g) | 330 |
【比較的カリウムが少ない野菜(生100gあたり)】
| 品目 | カリウム (mg) |
|---|---|
| きゅうり | 200 |
| レタス | 200 |
| たまねぎ | 150 |
| もやし | 69 |
- 芋類、かぼちゃ、ほうれん草、豆類はカリウムが多いと常に意識しましょう。
- 海藻類(わかめ、昆布、ひじき)や乾物(切干大根など)は、乾燥状態で極めて高カリウムです。水で戻す工程でカリウムは減りますが、戻し汁は絶対に使わないでください。
- 調理法が最重要!: これらの食品は後述する「茹でこぼし」「水さらし」を徹底することで、カリウムを30~50%程度減らすことが可能です。諦めずに上手に食卓に取り入れましょう。
3.【実践編】毎日の食事でカリウムを減らす調理の黄金ルール
カリウムは水に溶けやすい性質を持っています。この性質を利用すれば、調理の下ごしらえで含有量を大きく減らすことができます。以下の3つのルールを徹底しましょう。
ルール1:「切る」- 細かく、薄く
食材はできるだけ細かく、または薄く切りましょう。表面積が大きくなることで、水に触れる面積が増え、カリウムが溶け出しやすくなります。
ルール2:「さらす」- たっぷりの水で
切った野菜は、ボウルに入れてたっぷりの水に30分~1時間程度さらします。水はこまめに替えるか、流水にさらすとより効果的です。
ルール3:「茹でる・煮る」- 茹で汁は捨てる!
カリウムを減らす上で最も効果的なのが「茹でこぼし」です。
- たっぷりの湯を沸かします(食材の5~10倍量が目安)。
- 下ごしらえした食材を入れ、茹でます。
- 茹で汁は必ず捨ててください。カリウムが大量に溶け込んでいます。炒め物や和え物にする場合でも、一度この「茹でこぼし」の工程を挟むことが重要です。
- 煮汁・スープは飲まない: 煮物や鍋物、味噌汁の汁には、食材から溶け出したカリウムが豊富に含まれています。具だけを食べるようにし、汁は飲まない、または最小限にしましょう。
- 電子レンジ調理はカリウムが減らない: レンジでの加熱は、食材の水分で蒸す調理法です。水に溶かし出す工程がないため、カリウムはほとんど減りません。カリウム制限中は「茹でる」が基本と覚えましょう。
4. 外食・加工食品選びの「落とし穴」
自炊だけでなく、外食や市販の惣菜を利用する機会もあるでしょう。その際に注意すべきポイントを紹介します。
メニュー選びのポイント
- 生野菜・果物を避ける: サラダバーや付け合わせの生野菜、フルーツはカリウムが多い可能性があります。
- 芋類に注意: フライドポテト、ポテトサラダ、コロッケなどは避けましょう。
- 汁物は残す: ラーメンやうどんのスープ、定食の味噌汁は飲まないようにします。
加工食品の栄養成分表示をチェック
加工食品のパッケージ裏にある栄養成分表示を確認する習慣をつけましょう。カリウム量は表示義務がないため書かれていないことも多いですが、以下の点に注意してください。
【「減塩」商品の罠】
健康志向で「減塩」と書かれた醤油や味噌を選ぶ方も多いですが、これらには塩化ナトリウムの代わりに「塩化カリウム」が使用されていることがよくあります。これは、カリウム制限をしている方にとっては非常に危険です。原材料名に「塩化カリウム」や「調味料(無機塩等)」と記載がある場合は避けましょう。
【ポテト系スナックは厳禁】
ポテトチップスなどの芋を原料としたスナック菓子は、カリウムの塊です。1袋で1日の目標量を大きく超えてしまうこともあるため、絶対に避けましょう。
5. まとめ:正しい知識で、賢くカリウムと付き合おう
カリウム制限は、慣れるまでは難しく、食事の楽しみが減ってしまったと感じるかもしれません。しかし、正しい知識を身につければ、食べてはいけない食品はほとんどなく、「量を調整する」「調理法を工夫する」ことで、食事の幅を広げることができます。
最後に、食事療法を続ける上での大切な心構えです。
- 自己判断はしない: この記事は一般的な情報です。食事療法は必ず主治医や管理栄養士の指導のもとで行ってください。定期的に血液検査を受け、ご自身の状態に合った食事内容を確認することが重要です。
- 記録をつける: 食べたものを記録する習慣をつけると、カリウム摂取量を把握しやすくなり、管理栄養士への相談時にも役立ちます。
- 完璧を目指さない: 時には外食が続いたり、制限が難しい日もあるでしょう。神経質になりすぎず、長い目で見て継続していくことが最も大切です。
あなたの腎臓をいたわる食事療法は、未来の健康への投資です。この記事が、その一助となれば幸いです。



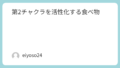
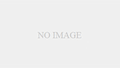
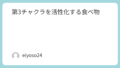
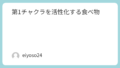
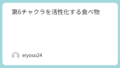
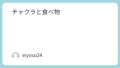
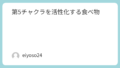
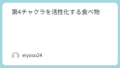
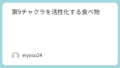
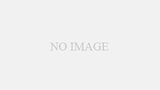
コメント